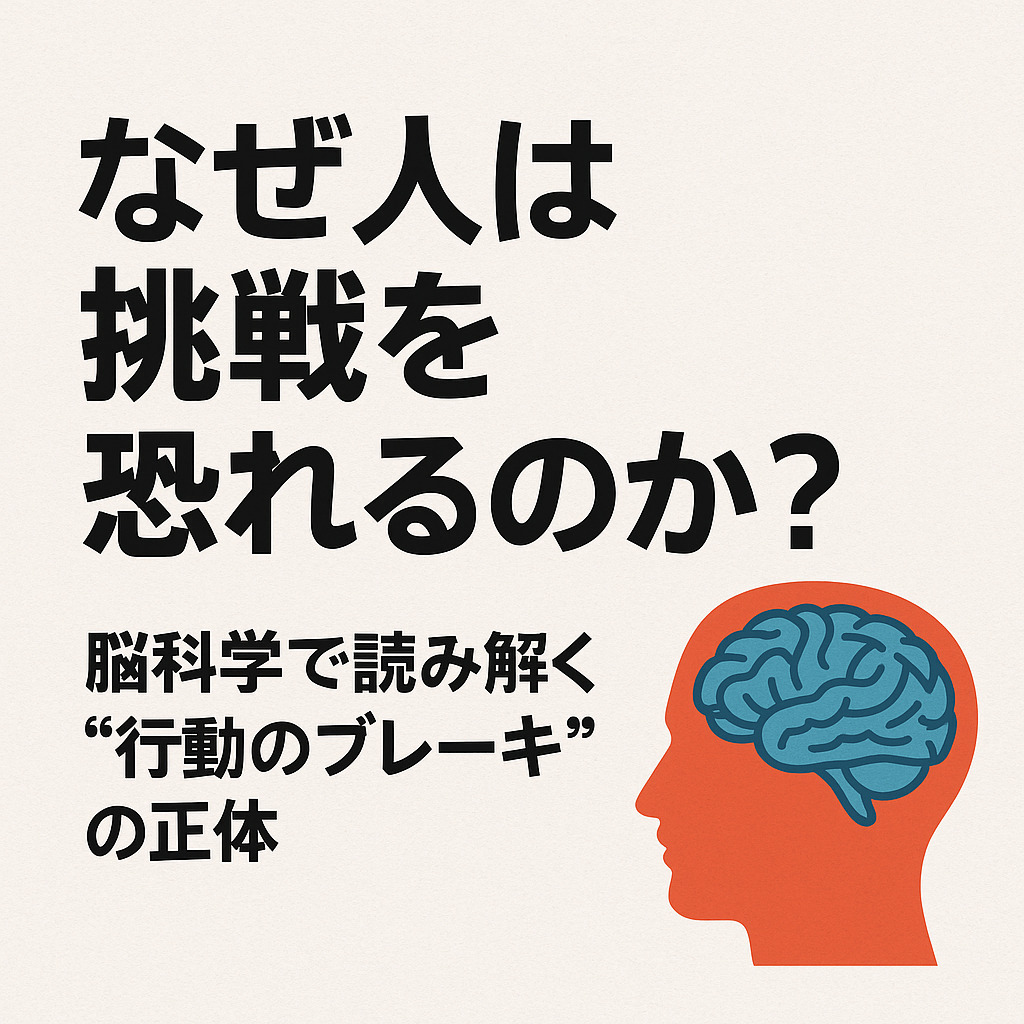「やる気が続かない…」は脳の仕業?|行動を変える“感情スイッチ”とは
「やらなきゃいけないのに、どうしても動けない…」
そんなふうに、自分を責めてしまったことはありませんか?
でも、それは意志の弱さのせいではありません。
実は「やる気が続かない」状態は、脳の“感情スイッチ”が関係しているのです。
本記事では、脳科学とSBT(スーパーブレイントレーニング)の視点から、
「やる気に左右されず行動を続ける方法」を解説します。
やる気が続かないのは『意志』のせいじゃない
私たちは「行動できない=意志が弱い」と思い込みがちです。
しかし、多くの場合、意志の問題ではなく脳の状態が関係しています。
特に不安・恐怖・恥ずかしさといった感情が強くなると、脳は“安全”を優先して行動を止めます。
つまり、やる気がなくなるのではなく、「やめておけ」というブレーキが無意識に働いているのです。
脳にある“感情スイッチ”が行動を止める理由
感情と行動をつなぐカギは「扁桃体(へんとうたい)」と「前頭前野」です。
扁桃体は恐怖や不安に敏感に反応し、脳の“危険検知装置”として働きます。
一方、前頭前野は「目標を考え、感情をコントロールする」役割があります。
この2つのバランスが崩れると、やる気があっても行動が止まるのです。
つまり、感情スイッチの影響で、脳が「今は動かないほうがいい」と判断してしまうのです。
感情スイッチを切り替える3つの方法
- 未来記憶を描く(ゴールを“臨場感”で感じる)
ゴールの映像を頭の中で描くことで、脳は「未来の快」を現在の行動へ変換しやすくなります。 - 小さな成功体験を記録する
成功の記憶は、扁桃体の反応を抑え、前向きな感情スイッチを入れる効果があります。 - セルフトーク(肯定的な言葉)を整える
「自分ならできる」「これで一歩前進」と脳に言い聞かせることで、行動への許可が出やすくなります。
脳科学から見た『やる気が続く人』の特徴
やる気が続く人は、「意志が強い」のではなく、脳の仕組みを味方につけている人です。
たとえば、ゴールを繰り返しイメージする習慣や、日々の小さな達成に喜びを見出す姿勢など、
無意識レベルで脳のスイッチを「行動モード」に保っています。
SBTではこれを“成功する脳の使い方”として体系的にトレーニングしていきます。
行動が変わると、未来が変わる
やる気に頼らず行動できるようになると、人生の主導権は自分に戻ってきます。
「また続かなかった…」ではなく、「自分は変われる脳を持っている」という感覚が育ち始めます。
まずは、今日できる小さな1歩から。
そして、もし本気で「挑戦できる脳」を育てたいなら、下記からメルマガにご登録ください。
※この記事が参考になったら、ぜひ他の「行動ブレーキ」関連の記事もチェックしてみてください。